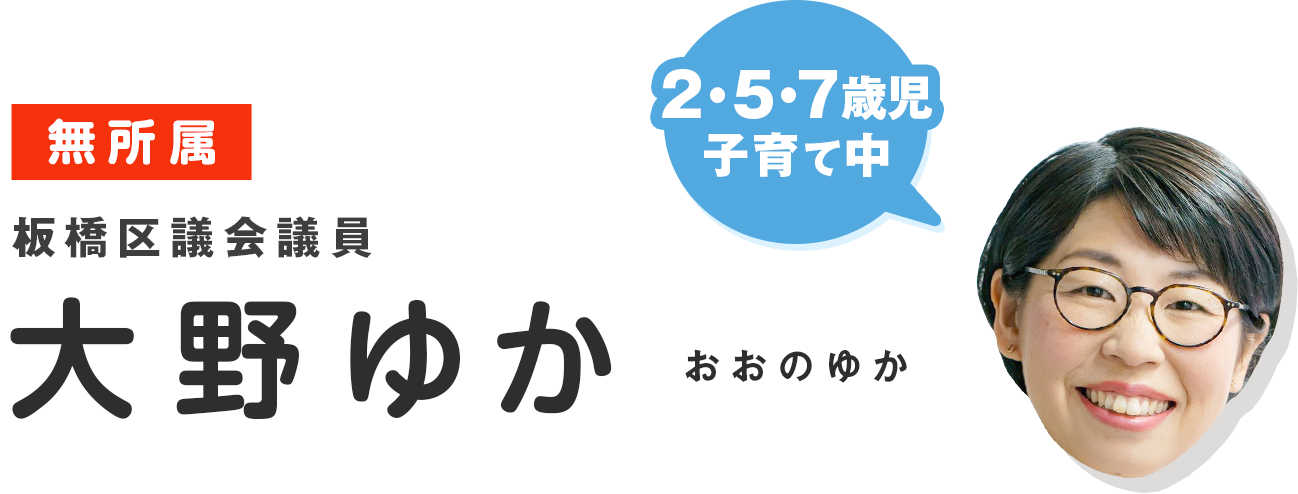2024年06月28日
ウォーターセーフティー授業の視察へ
昨日は子どもの事故予防議連のメンバーで町田市立小山田南小学校へ
伺いました。

先日の海のそなえシンポジウムに続き、水辺の事故予防を学びました。
日本ライフセービング協会によるウォーターセーフティ授業です。
板橋区では、2021年に新河岸川で小学生の悲しい水難事故が発生しており、周辺小学校では今回のようなウォーターセーフティー授業が昨年度実施をされています。
授業は、まずは日本ライフセービング協会の松本先生から、全校生徒へ向けた一斉配信のお話がありました。1年生でも分かりやすい内容でした。
https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/
(こちらから動画が見れます)

続いて6年生を対象としたプール授業。
スタートから、松本先生が溺れる演技をします。
「この時、みんなならどうする?」という声かけから始まりました。
「救急車を呼ぶ→10分かかるから沈んでしまうよね」
「浮具を投げる」
→これがなかなか大変でビート板7枚くらい投げてやっとでした

「絶対に助けようと飛び込んではいけない」
ということを再確認していました。
終始、子どもたちに問いかけながら進む授業で、90分の授業を楽しく積極的に受けている印象でした。
プログラムその他に3つ
⚪︎プールサイドに上がれなくなっている人を持ち上げる方法
⚪︎ライフジャケット着用

⚪︎ライフジャケットを着ていか泳ぎ

特にライフジャケットを着用した時には「こんな浮くのすげー」など驚きの声が聞こえてきました。股の紐を通していないと、水に入ると顔面に浮いて着てしまうので、股紐の必要性を実体験している子どももいました。
先生からも来年も続けてほしいという声がありました。
着衣水泳が各学校の高学年で実施されていると思いますが、その時間を今回の授業枠として活用することも出来るそうです。
夏休みで、海や川に遊びに行くご家庭も多いと思います。
全ての子ども達が水辺の安全授業をしっかり受けられるようにするべきだと再認識しました。
70年ほど前の紫雲丸沈没事故で、たくさんの児童がなくなってしまったことをきっかけに学校では水泳授業が必修になりました。
現在は、暑さや老朽化などプール実施にも課題が出てきています。
時間数も短くなり、水泳を学ぶというのは実質的に難しい現状があります。
限られた時間を子どもの安全のために活用していく方法も検討していきます。
今回の学びで得たことを板橋区にも伝えていきます。
コドジコ議連水辺の安全対策委員長藤條多摩市議、幹事長の矢口町田市議、大変貴重な機会を頂きましてありがとうございました😊
Copyright (c) 大野ゆか. All rights reserved.